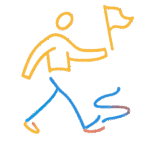このレポートは、「学びの時間」の中で行ったスーパーバイズの内容の一部をまとめたものです。
(「学びの時間」とは、NPO法人クリオネの家が会員向けに行っている勉強会です。)
納得のできたとき何かが変わる
子どもが“いい子”と言われるような行動をとるのは、なぜなのでしょうか。
人は、望ましい結果を手に入れることができた行動を繰り返そうとします。
子どもにとっての望ましい結果とは、周囲の大人(特に親)の笑顔です。
どんな素敵な言葉を並べられるより、笑顔を見せてほしい。
それが子どもの本音のようです。
「好き」や「嫌い」の基準は、早いうちから子どもの中につくられます。
しかし、「何が正しい」や「何をするのがいいこと」といったことは学んでいる最中。
だからこそ、大人の示す基準がとても大切になります。
それなのに、基準が曖昧だったり、大人の気分で変わってしまう。
よくないことは教えてくれても、何をすることがいいことなのかを示してくれない。
こんな状態になったとしたら、
子どもが、イライラしたり、落ち込んだりするのは当然のことです。
もしも、子どもが、イライラしたり、落ち込んでいたら、
まずは、話を聞いてから
「こんな人になってほしい」を伝えてあげる。
- 優しい人になってほしい
- 自分の気持ちを言える人になってほしい
- 自分のことは自分でできる人になってほしい
そして、そこで起きた行動や言動は肯定的に受け止めること。
否定的な姿勢は、私は正しくてあなたは間違っているという雰囲気を作ってしまいます。
未熟な子どもが、いきなり大人の求めるレベルのことをできるはずはありません。
「こうすれば笑顔になってもらえるんだ」という体験を、少しずつ積み重ねていけるように、サポートすることが必要です。
人は、意識をむけることの多いことを引き寄せてしまいます。
「嫌だったこと」に意識が向き続けていれば、
それが頭の中から消えなくなることも少なくありません。
しかし、誰もが自分の感じていることを「正しい」と思うものです。
感じ方を変えようとか、捉え方を変えようといった
「自分が変われば何かが変わる」
そんな視点に立つのは簡単ではありません。
では、どんなときに
「自分が変われば何かが変わる」
そんな視点に立てるのでしょうか。
それは、“納得のできたとき”です。
・何が起こっているのかを理解できて
・その状況を打開するために自分の力が必要
それを納得できたときです。
カウンセリングの知識とスキルがあれば、
その納得感をつくりだすことをサポートできるはずです。
「周囲から求められること」と「今の自分にできること」
そこにギャップがあるということは、その社会で活躍するための伸びしろがある証拠。
少しずつでも、できることを増やしていける。
そんな人になっていけるといいですね。
(星野伸明)